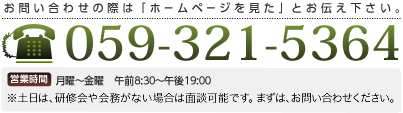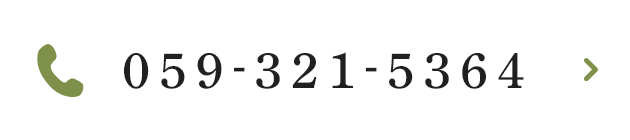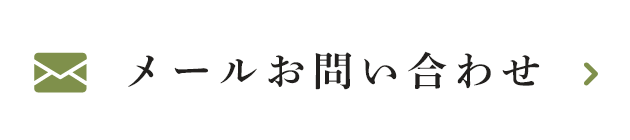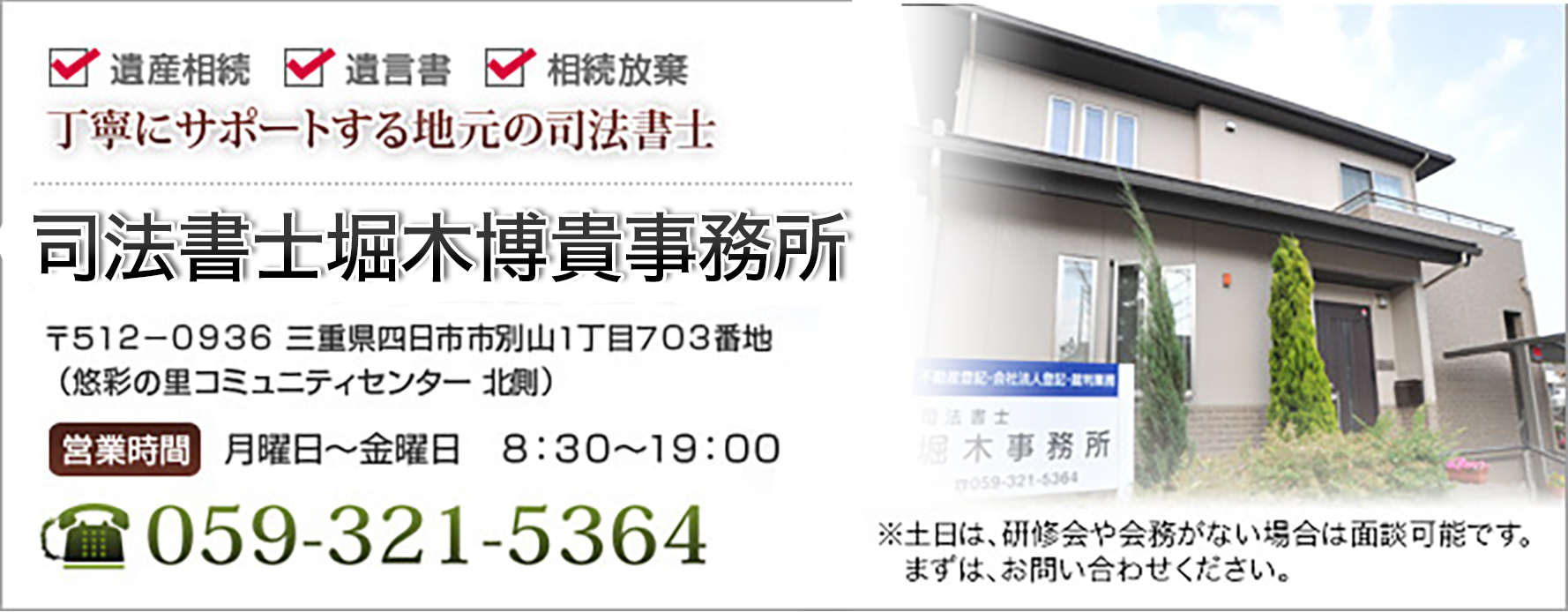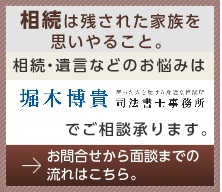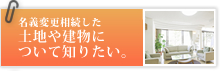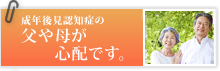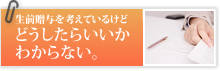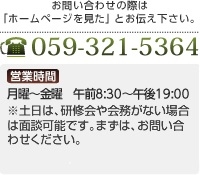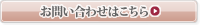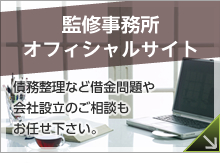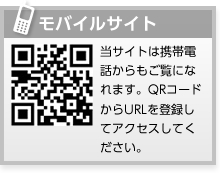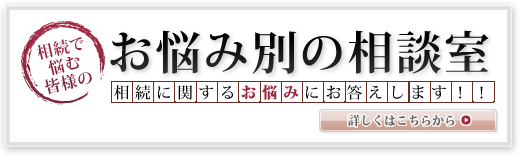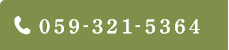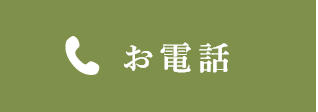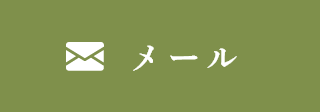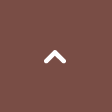成年後見制度について
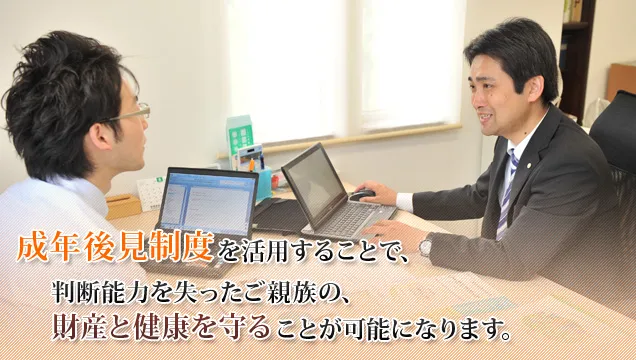
認知症や知的障害などにより判断能力が低下してきたご親族がいらっしゃる場合、さまざまな問題が発生してきます。
財産の管理、悪質な商法に引っかかったときの契約の解除、老人ホームなどの施設に入るための資金の捻出・・・。
判断能力のない高齢者の代理として、財産の管理や介護の契約などを行う人を、成年後見人といい、その後見人を定める制度が成年後見制度です。
司法書士堀木博貴事務所は、成年後見人制度を法的な立場からサポートするリーガルサポートの会員であり、リーガルサポートの会務を通じて、この制度に深く関わっています。

成年後見制度は、高齢者の利益を守るための制度

判断能力がなくなった高齢者の方の財産を管理し、施設や看護、介護などのサービスを継続的に活用する権利を守るための制度です。
成年後見人制度を活用しますと、対象者に多額の資産がある場合には、裁判所が定める専門職後見人が財産の管理にあたります。また、場合によっては、平成24年2月からは後見制度支援信託が適用されるようになりました。
それは、後見人(親族・専門職)による資産の横領を防ぐための措置です。
リーガルサポート会員として、成年後見制度に協力してきました

当事務所所長の堀木は、公益社団法人成年後見リーガルサポートの会員であり、会務や実務を通して成年後見制度に精通しています。現在までに、十数人の方々の専門職後見人を務めています。
リーガルサポートの会員が法定後見人を担当する場合には、通帳のコピーを添付した報告書の提出が義務づけられています。半年に一度、会のチェックが行われ、報告書と、財産のチェックにより不正行為を防止しています。
長く制度にかかわってきたから、できることがあります。

親族の方が、高齢者の生活を心配して、成年後見制度の相談にこられるケースに対しても、しっかりと対応できます。この制度は、経験を踏まないとわからないことがたくさんあります。堀木の経験が、みなさまの心配の解決にお役にたちます。
ご相談の流れ
ここでは、申立手数料などの費用が発生します。
※当事務所では、多くの経験をしてきた堀木が、聞き取りなどの調査もサポートします。ご安心ください。

また、最適な後見人を選定します。
財産が多い方や、親族間で同意が得られない場合、遺産分割を伴うなど、複雑な案件の場合は、原則的に専門職後見人が選出されます。
成年後見制度には、法定後見人と任意後見人の2種類があります。
ご説明した流れは、法定後見人のケースで、対象者ご本人がすでに判断能力を失った場合に、本人や四親等内の親族等が申し出て、後見人を選出する方法です。
もうひとつの任意後見人とは、ご本人が判断力をお持ちのうちに、あらかじめ誰か任意の人を後見人に選出しておくことができる制度です。こちらは公正証書の作成により行います。
任意後見制度では、後見人を誰にするか、委任する範囲はどうするかなどを、ご本人と後見人とが話し合うことで自由に決めることができます。