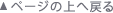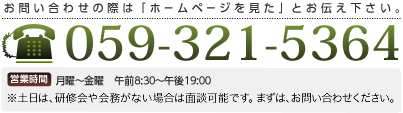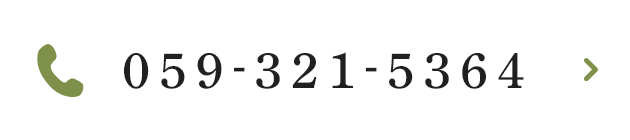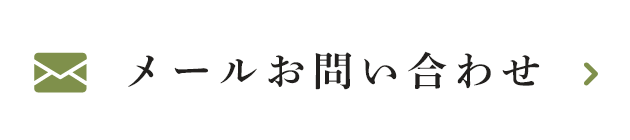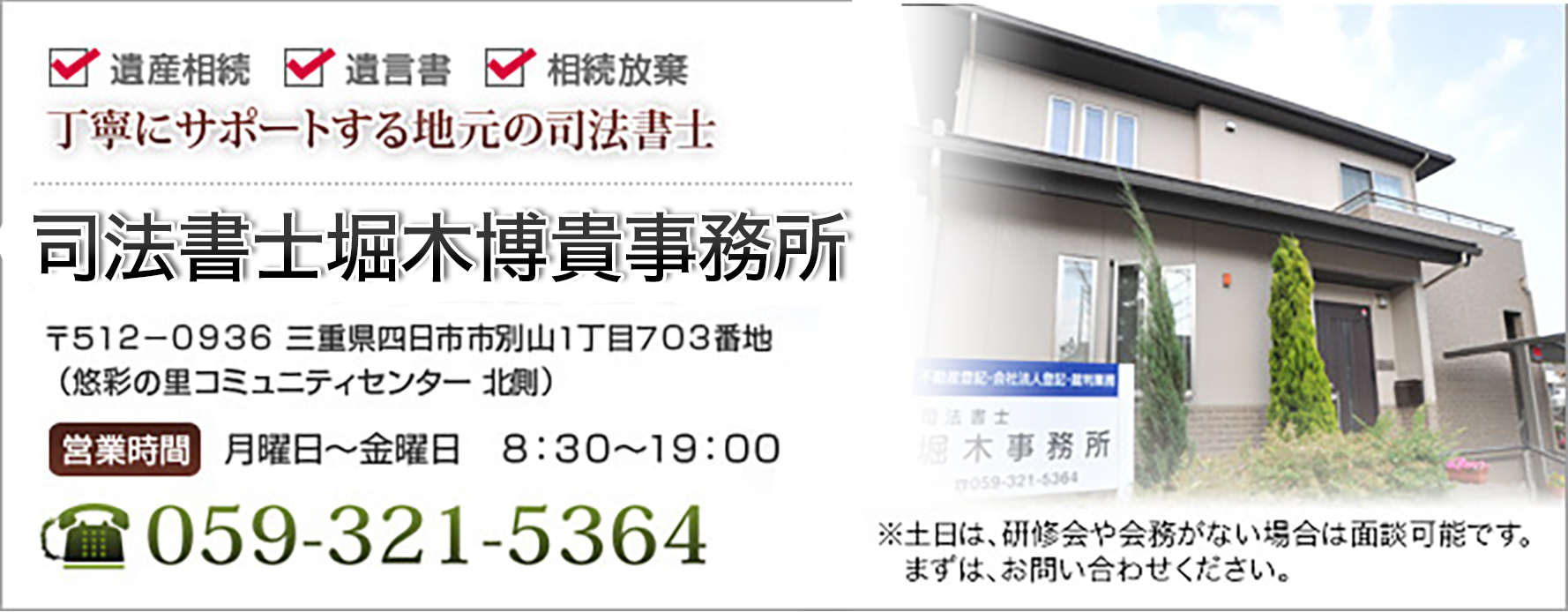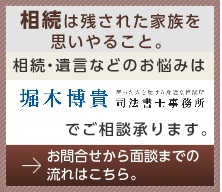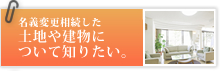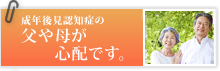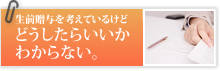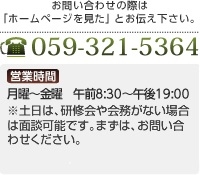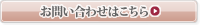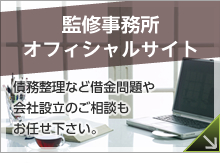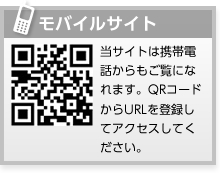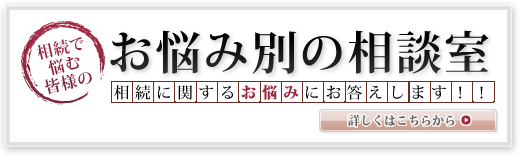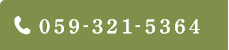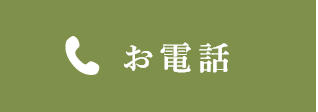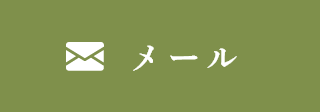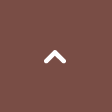相続の相談室「Q&A」
- 遺言書があった場合はどのように対処すれば良いですか?
- 故人の銀行の預金の出金についてはどうすれば良いんでしょうか?
- 遺言書があるかどうかを調べる方法はあるんでしょうか?
- 不動産の名義の変更することは出来ますか?
- 相続財産があるかどうかを調査する方法はあるんでしょうか?
- 戸籍の調査はどうやって行えば良いの?
- 相続があったときに遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないのでしょうか?
- 相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?
- 遺言には、いくつぐらい種類があるのですか?
- 相続人が認知症の場合はどうすれば良いですか?
- 相続のある前に相談することはできますか?
- 相続放棄できるはいつでも出来るのでしょうか?
- どのような場合に相続放棄が必要でしょうか?
遺言書があった場合はどのように対処すれば良いですか?
すぐに開封はしないでください。慎重に保管してください。
故人の遺言書を発見したら、以下の点にご注意ください。
•遺言書が封筒などに入れられている場合、検認手続が終了するまでは絶対に開封しないこと。
•金庫等に保管すること。紛失・汚損・破損など避けるため、
遺言書は検認手続が終了するまでは、絶対に開封してはいけません。
遺言書を勝手に開封してしまった場合、あなたに5万円以下の過料(罰金のようなもの)の支払を命じられてます。
中を見たい気持ちはわかりますが、
こらえていただいて、法律の定める手順に沿って進めていきましょう。
遺言には3種類の遺言があります。
「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」です。
このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言の遺言書を発見した場合には、
遺言書の検認手続を家庭裁判所に請求しなければなりません。
検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続のことをいいます。
遺言書の検認手続きを請求しなければ、
あなたは勝手に遺言書を開封したと判断される場合があり、
同じく5万円以下の過料の支払を命じられる恐れがあります。
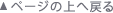
故人の銀行の預金の出金についてはどうすれば良いんでしょうか?
被相続人の銀行口座は、金融機関に死亡を報告し相続が発生すると分かった時点で、凍結処理が行われます。
故人の為のお葬式のご準備等に、現金が必要になると思います。
そして、カードのお引落や、水道・電気・ガスといった公共料金の引落等もストップしてしまいます。
冷静に考えると、分割後に各相続人に割り当てられた金額までは、お金を使用しても問題ないように思います。
しかし、実際には銀行へ相続人全員の署名捺印と印鑑証明の提出、もしくは遺産分割協議書を添付して請求を行う必要があります。
そして、相続人である事を証明する為には、相続人全員の戸籍謄本を用意しなくてはなりません。
戸籍収集は、場合によっては非常に手間と労力と時間がかかる事があります。
司法書士堀木博貴事務所では諸々の手続きについてトータルでサポートさせていただきます。